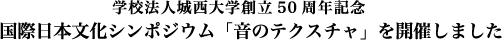

挨拶する水田理事長
2016年1月13、14日、学校法人城西大学(水田宗子理事長)は、前近代の日本文化における「音や声」をテーマとした国際日本文化シンポジウム「音のテクスチャ」(TEXTURES of SOUND)を、東京紀尾井町キャンパス1号棟ホールで開催しました。学校法人創立50周年を記念し、城西国際大学日本研究センターとヨーロピアンセンターが主催、国際人文学部と国際学術文化振興センターが共催しました。各国で活躍する高名な日本研究者による先端的な研究成果の発表があり、オーラリティ(声の文化)や音楽の果たす役割などについて活発な意見交換が行われました。
13日の開会式で、水田理事長は「私どもは『世界の中の日本』という講座を手掛けてきました。今回のシンポジウムはその集大成として企画したものです。先端的なテーマを新しい文化の課題として取り上げることによって、人文科学全体の勉強の仕方、あり方に示唆をいただけるシンポジウムにしたいと思います。新しい研究の成果をお聞きいただきたい」と挨拶しました。また、城西大学、城西国際大学の杉林堅次副学長は「前近代の日本の美術、音楽、文学に関して議論していただくという画期的なテーマと内容を立案していただき光栄に思っています」と、参加の研究者の方々に対する感謝の言葉を述べました。
その後、コロンビア大学のハルオ・シラネ教授が「共同的記憶の形成における声、身体、音楽:中世日本の説話のメディア再考」と題して基調講演。シンポジウムを記念して琵琶奏者の川嶋信子さんが、『平家物語』から「祇園精舎」「福原落」「壇ノ浦」の3曲を披露しました。
この日は、アン・バーリントン駐日アイルランド大使やイシュトヴァーン・セルダヘイ駐日ハンガリー大使、マグヌス・ローバック駐日スウェーデン大使や青柳正規文化庁長官ら多数の方々の出席をいただきました。また、研究者や両大学の教職員、学生らが参加しました。

基調講演するシラネ教授

川嶋さんの琵琶演奏に聴き入る参加者
2日目の14日は、以下のプログラムで研究発表と意見交換、質疑応答が行われました。
【午前】
・ ユージン・ワン教授(ハーバード大学)「正倉院の琴:どのような曲を弾いているのか?」
・ アシュトン・ラザラス准教授(シカゴ大学)「初期中世日本の民俗芸能とサウンドスケープ」
・ 大内典教授(宮城学院女子大学)「記されないものは何か―仏教声楽の記譜法」
▽意見交換と質疑応答
コメンテーター:ディディエ・ダヴァン教授(フランス国立極東学院・東京)
【午後】
・ メリッサ・マコーミック教授(ハーバード大学)「声を見る:日本の絵巻における対話描写とメタナラティブ」
・ 岡田美也子准教授(城西国際大学)「琴を弾く女―中世説話の音とイメージ」
▽意見交換と質疑応答
コメンテーター:ハルオ・シラネ教授(コロンビア大学)
・ ユディット・アロカイ教授(ハイデルベルク大学)「和歌のオーラリティに対する江戸時代後期におけるアプローチ
―詩的言語の即時性を探る」
・ タイモン・スクリーチ教授(ロンドン大学)「初期近代の東洋と西洋における絵画のパフォーマンス」
▽意見交換と質疑応答
コメンテーター:ユキオ・リピット教授(ハーバード大学)
|
研究発表をするワン教授 |
研究発表をするマコーミック教授 |

研究発表をするスクリーチ教授

コメンテーターのリピット教授
最後に今回のシンポジウムの企画やプログラムの作成に尽力いただいたメリッサ・マコーミック教授が「城西大学には主催の労を取っていただきありがとうございました。研究者に皆さまには、高いレベルで新しいテーマに取り組んでいただき感謝いたします」などと、まとめのスピーチをされました。
両日ともシンポジウム後は、レセプションが行われ、著名な研究者を囲んで歓談のひと時を過ごしました。

特別展示された浮世絵に見入る参加者

